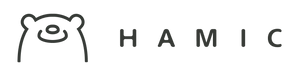【情報モラル教育】小学生に教えたい「あひルのおやコ」ってどういう意味?
皆さん、こんにちは。小学生姉妹と0歳ベビーを子育て中の、はみっく編集部ライターです。先日娘が、小学校で行われた情報モラルに関する授業の資料を持ち帰ってきました。「今ってこんなことも学校で習うんだね〜」と感心しながら眺めていると、「『あひるのおやコ』を忘れずに!」という一文が目に入りました。娘に聞いてみると、スマホなどの情報端末を使う上で、注意することをまとめた標語らしく、その標語を元に授業を進めていたのだそうです。

と言うことで、今回は小学生に教えたい「あひるのおやコ」について、皆さんにもシェアしたいと思います!
| 関連記事▽ |
「あひルのおやコ」は警察発信の防犯標語!

[画像:兵庫県警察 会いに行かない ルールを守る 載せない 思いやり - 兵庫県警察]
「あひルのおやコ」は、兵庫県警察サイバー犯罪対策課が考えた防犯標語で、情報端末を使う上で気をつけたいポイントを、子どもにもわかりやすく・覚えやすくしたフレーズです。
誘拐や不審者対策の防犯標語「いかのおすし」や、災害時の避難標語「おはしも」と同じく、気をつけるポイントの頭文字を取って標語にされています。
あひルのおやコの意味は?
-
あ…会いに行かない
-
ひ…秘密にする
-
ル…ルールを守る
-
の…載せない
-
お…思いやり
-
や…やっておこう!フィルタリング
-
コ…コミュニケーションを大切に
ここからは、一つずつについて詳しく見ていきましょう。
あ:会いに行かない

あひルのおやコの一文字目は、「ネットで知り合った人に会いに行かない」の「あ」です。小学生のうちは、第三者とネットで繋がること自体をなるべく避けたいところですが、知らない人と知り合うことを目的としなくても、ゲームアプリなどで「結果的に」繋がってしまう場合も少なくありません。そんな時でも、やりとりをして、現実世界で会おうとしなければ、最悪の事態は防げます。
| 小5長女が「会いにきてもらうのはいいってこと?」と言ってきたので、揚げ足をとってくるタイプのお子さんなら、先回りしてそのあたりも釘を刺しておくといいかもしれません…。 |
ひ:秘密にする
パスワードやスマホのロックナンバーは、どんなに仲のいいお友達にも、教えないように伝えておきましょう。お友達が別の人に教えてしまわないとも限りませんし、SNSでのなりすましやアプリへの課金など、トラブルが起きた際には、パスワードを教えたお友達のことも疑わざるを得なくなってしまいます。また、家族であっても、パスワードをSNSやメッセージを介して聞かれた際には注意が必要です。
ル:ルールを作る
情報端末を使う上では、利用時間や利用する場所などのルールを作ることが大切です。個人的には、親が子どもにルールを押し付けるのではなく、家族で話し合って、子どもにも納得してもらった上で運用するのがポイントかな、と感じています。

忘れてはいけないのが、あらかじめ決めておいたルールを破った時に、どうするかというルールです。うちでは、決めているルールを子どもが破ったら、メッセージと通話以外のスマホの機能をロックすることにしています。宿題が終わるまではスマホを触らない、など子どもが嫌だと感じる内容で、かつ、安全を脅かさない内容のペナルティを考えてみましょう!
の:ネットに載せない
個人情報や、住所などが特定される要素のある写真は、ネットに載せないようにしましょう。名前や住所を載せないのは、なんとなく子どもでも理解しているようですが、ご近所にある施設の名称や地名を載せてしまったり、住所が書いてある電柱や、フルネームが書かれた体操服の写真をアップしてしまうなど、ついうっかりで個人情報を流出させてしまう場合もあります。ネット上では、一度流出してしまった情報や写真を全て回収することは難しいとされています。大切な情報は、しっかり自分で守るようにしましょう。
お:思いやりのある書き込みを
SNSでの中傷や悪意ある書き込みは、誰かを傷つける場合があります。子どもは大人と比べて、物事の行方を想像する力が弱いため、顔の見えないネット上の誰かに配慮することが難しいようです。よく知っている友達だとしても、相手の顔が見えないメッセージのやりとりでは、誤解が生じるケースは少なくありません。メッセージやコメントを送信する前には、「この文面は、相手を嫌な気分にさせないかな?」と再度確認する癖をつけておくといいかもしれません。
や:やっておこう、フィルタリング
有害サイトにアクセスできないようにしたり、対象年齢外のアプリをインストールできないようにするフィルタリングは、端末の設定や子ども向けの端末管理サービス(アプリ)を利用して行います。わが家で言うと、長女はiPhoneのスクリーンタイム、次女はGoogleのファミリーリンクというアプリを利用しています。

フィルタリングをしたからといって完全には遮断できない部分はあるので、そのあたりは周りの大人が注意して見ておいてあげるといいでしょう。(サイト自体は普通のまとめサイトなのに際どい広告がでるサイトなどはフィルタリングには引っかからないので、個別でブロックも!)
コ:コミュニケーションを大切に
飲食店で食事が来るまでの間、親子でそれぞれ無言でスマホを見ている…なんていうシーンを見かけることはありませんか?私自身も、少しの空き時間ができたら、手持ち無沙汰に感じて、ついスマホを見てしまうのですが、子どもと一緒にいる時にはなるべくスマホに夢中にならないよう注意しています。子どもだけでなく、パパママも、友達や家族と過ごす時間を大切に、デジタルを介さないコミュニケーションも楽しみたいですね。
【番外編】教え方に迷ったら→キッズ携帯・キッズスマホで実践教育を!
ここまで、ネットリテラシーを学ぶ上で大切なポイントを挙げてきましたが、「これ全部、子どもに理解させるのって大変なんじゃ…」と感じている親御さんもおられるかもしれません。確かに、一気にこれだけのことを伝えられても、子どもも理解しきれず、トラブルになってから「そういえばそんなの聞いたことある気がする…」となる可能性も。

思春期に入ってしまうと、親の言うことを素直に受け入れづらくなるので、子どもにしっかりとルールを定着させるのであれば、低年齢のうちに親が見守りながら、随時教えていけるような実践練習の機会を作るのがおすすめです。
HamicMIELSはしっかり見守れて練習にも◎

我が家の次女が使っているHamicMIELSは、 Googleのファミリーリンクでフィルタリングができるだけでなく、Hamicアプリを使うと、子どもが他の人としているメッセージのやりとりを見守ることもできます。スマホデビューして、いきなりネット社会に放り込むのではなく、家族や親しい友達などの安全性の高い環境で、慣らし教育をするワンクッションを挟むと安心ですよ!
まとめ:情報リテラシー教育でネットの危険から子どもを守ろう!
本記事では、情報リテラシーに関する大事なことをまとめた標語「あひルのおやコ」について解説をしてきました。子どもには特に大切な内容ばかりなので、しっかり親子でシェアして、普段から意識できるようになるといいかもしれません。
SNSいじめや不適切動画・課金トラブル・闇バイトへの誘いなど、子どもをネットに触れさせるのが怖くなるような問題はたくさんありますが、適切に使えば、過剰に恐れる必要はありません!情報リテラシーについて、しっかり親子で話し合って、どうすれば未来の我が子を守れるか考えてみて下さいね。